若手弁理士に聞く、付記試験のリアル ~「早めに受けてよかった」と感じたホンネ~
公開日: 2025-07-05
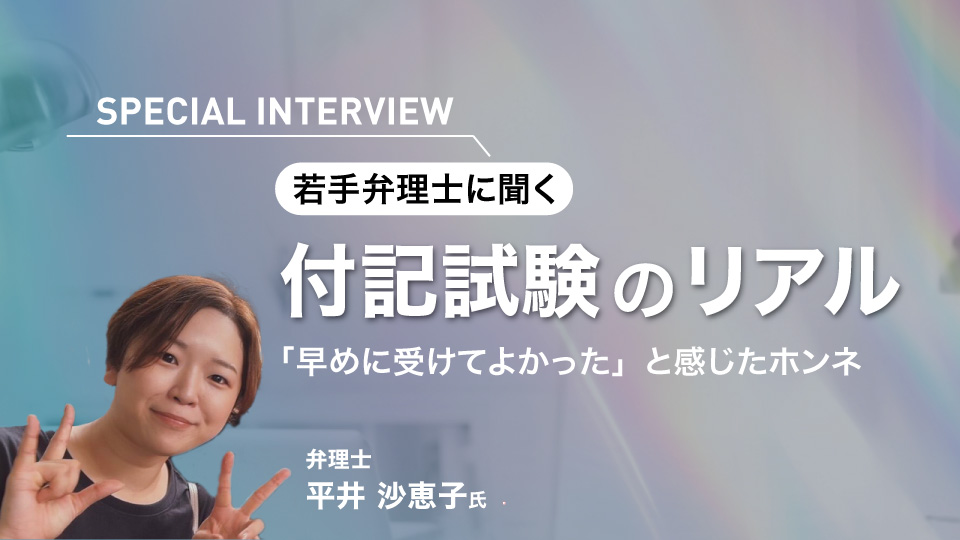
弁理士として活躍する中で、いつかは…と思いつつもなかなか手が出せない「付記弁理士試験」🌀
今回は実際に付記試験に合格した若手弁理士・平井さんに話を聞き、試験の実態や学習の工夫、合格後の変化についてリアルな声をまとめました。
\最新の求人情報をチェック!/
商標担当の若手弁理士、キャリアのスタート
新卒で特許事務所に入所し、約5年間特許事務を経験。その後、より幅広い業務を求めて法律事務所に転職。2023年に弁理士登録を行い、現在は商標の出願・調査・警告対応などを中心に業務を担っているとのことです。
商標業務において、より踏み込んだ対応をするには…と考え、付記弁理士の取得を決意🎯
「早めに受けたほうがいい」——先輩のアドバイスが背中を押す
試験の主なポイントである民法・民訴法のうち、民訴法に触れるのは初めてだったものの、周囲の弁理士からは「早めに受けた方がいいよ」「知識も答案力も、弁理士試験から時間とともに衰えるよ」といった声が多く届いていたそう。
まだ実務経験が浅い弁理士2年目のタイミングでチャレンジを決めた背景には、そんなアドバイスも影響していたようです✨
付記試験までの流れ
受験には「能力担保研修」の受講が必須。
例年、以下のような流れで進行します📅
・春ごろから研修スタート(約4か月間)
平日クラス・土曜クラスがある。隔週開催で、内容は民法・民訴法・特許判例など。
・事前準備として、弁理士会のEラーニングで基礎知識をインプット
・秋ごろに本試験(記述式)を受験
平日は仕事、勉強は主に週末でカバー
平日は業務に追われて勉強時間を確保するのが難しく、主に土日で学習時間を捻出。
Eラーニングは1コマ約3時間×12回ほどで、苦手分野は繰り返し視聴📺
直前期は、週に20〜30時間の勉強時間を確保し、重点的に対策を行ったそうです。
同じ研修クラスのメンバーと情報共有しながら進めることで、勉強のペースも保ちやすかったとのこと🏃♂️💨
気になる費用と補助制度
おおまかな費用感としては以下のとおり💰
・研修、Eラーニング、ゼミなど:計30〜40万円
・費用補助があるかは事務所による → 所属先の制度は事前確認が重要📝
合格後、すぐに業務が変わるわけではないけれど
取得前から一部の警告案件等に関与していたこともあり、合格後すぐに仕事内容が劇的に変わるというわけではないとのこと。
ただ、民法や民訴法の知識が身についたことで、業務の理解が深まった実感はあるようです📚
若手のうちに受けるメリット
「知識が新しいうちに受けられる」「時間の融通がききやすい」といった点は、若手ならではのアドバンテージ🌱
「もっと早く準備しておけばよかった」という反省もありつつ、仲間と一緒に取り組めたことが心の支えになったとのことです。
これから受ける人へのアドバイス
これから付記試験を目指す方へのヒント🧭
・民法や民訴法の内容を“面白い”と思えるかどうかがカギ🔑
・勉強仲間と一緒に進めることでモチベーション維持◎
・過去問を何度も解き、記述の型を身体に染み込ませる
・情報が少ない分、自分から動いて集める意識が重要
また、特許庁のホームページにある過去問・解説資料も非常に有用です。予備校的な存在がないため、公式情報の読み込みも欠かせません。
取得して損なし。未来の選択肢を広げる一歩に
付記弁理士資格を取ったからといって、すぐに仕事や収入が変わるわけではない。
それでも、いざ紛争案件や裁判対応に携わる場面が来たとき、大きな武器になるのは間違いありません💡
弁理士試験合格後や、年齢が若いうちにチャレンジした経験は、きっと将来のキャリアにおいて力強い支えになるでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございました!
知財塾ではお気軽に無料キャリア相談をお申込みいただけます。